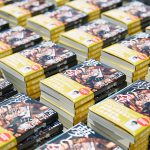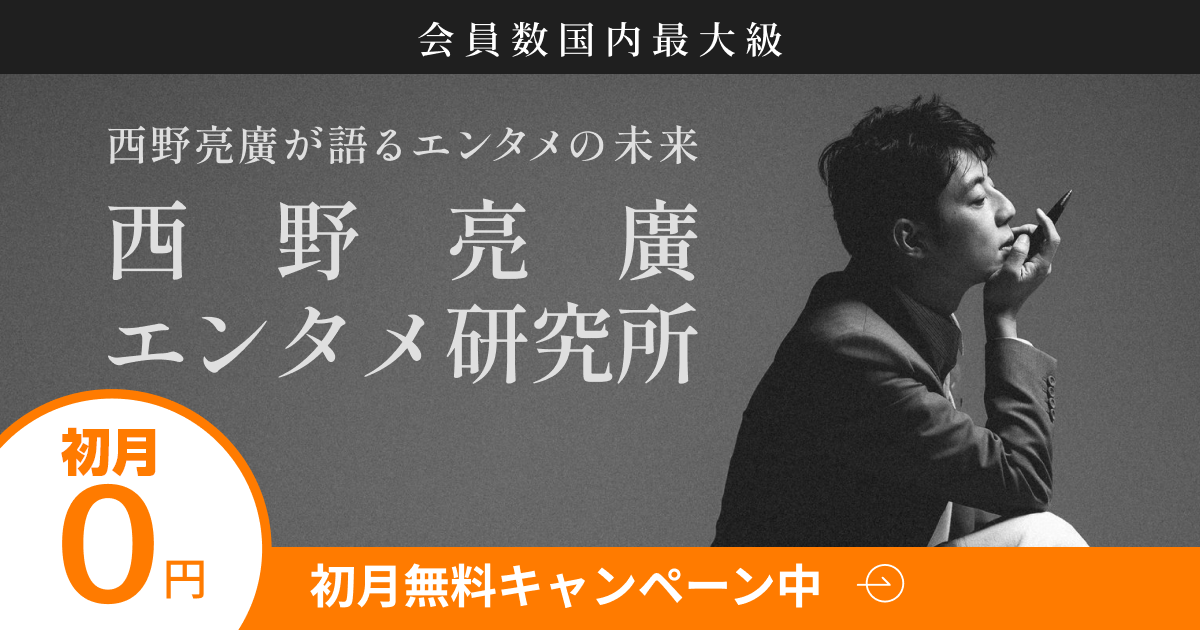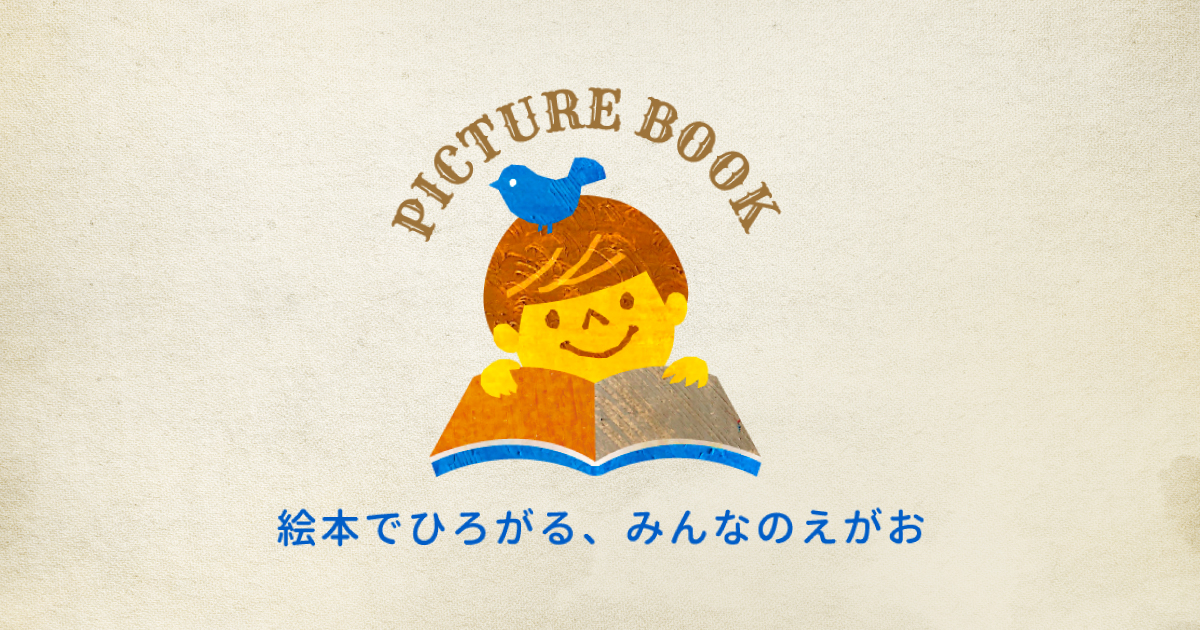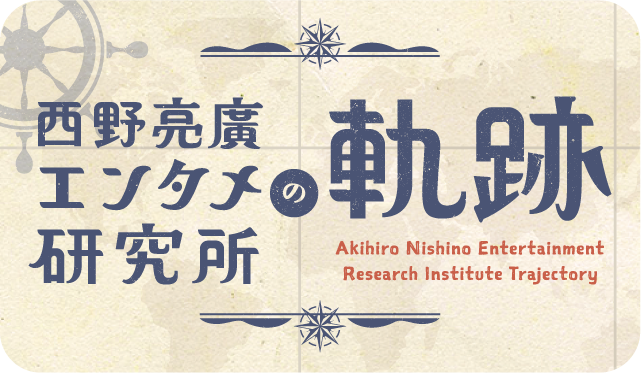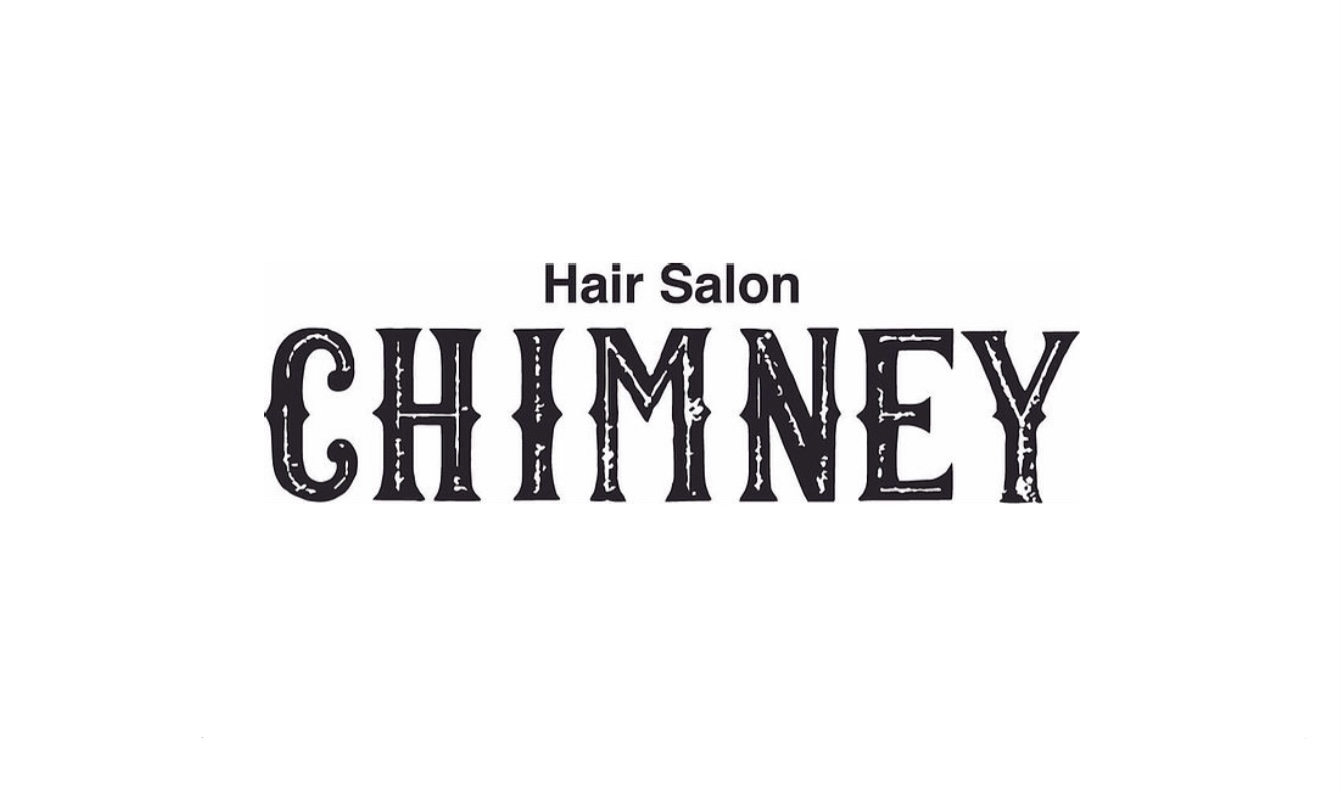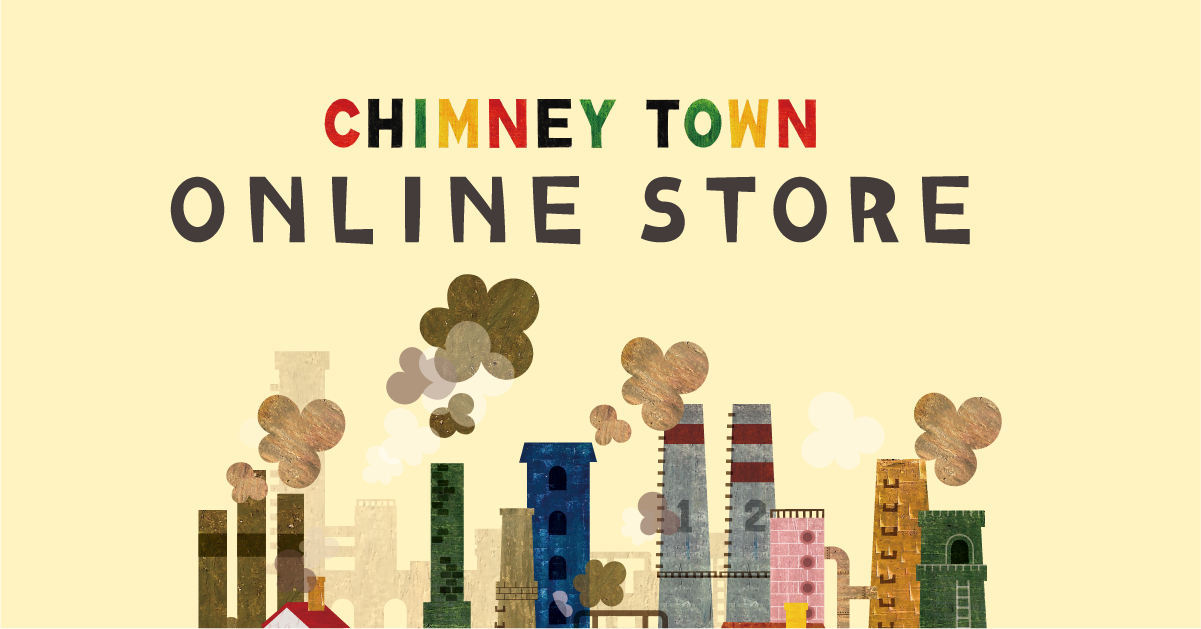『撤退』の判断はリーダーにしかできない

※この記事は、2022年3月4日に掲載された「GOETHE」(幻冬舎)の記事より一部転載しています。
さっきまでボンヤリと考えていて、突然、ものすごくシックリきたことなので、産地直送でお届けします。
「名前をつける」という儀式
『えんとつ町のプペル』では、煙突掃除屋の少年「ルビッチ」が、ハロウィンの夜にやってきたゴミ人間に、「プペル」という名前をつけるシーンがあります。
絵本と映画とミュージカルと歌舞伎で、それぞれストーリーは違っていたりするのですが、この「名前をつけるシーン」だけは必ず入れています。
その理由を説明には、まず「名前をつけるとはどういうことか?」を共有しておく必要があります。
まわりくどい話が苦手なので、いきなり結論を言っちゃうと、「名前をつける」というのは、「生み出す」や「存在を認める」という意味(行為)です。
今、僕らの目の前には「空気」がありますが、これも「空気」という名前がなければ、僕らは「空気」を認識できません。
感情もそう。
名前がついたことによって、生まれた感情がたくさんあります。
「さみしい」という名前をつけたことによって、「きっと、今の僕の気持ちは『さみしい』なんだ」と認識するようになり、「さみしい」が大量発生した。
立場を利用した攻撃に対して「パワハラ」という名前をつけたことによって、「パワハラはダメだよね」と社会が一歩前に進みました。
「パワハラ」という名前がつく前のクリエイティブの現場は、「こんなこともできねぇやつは、死んじまえ!」という言葉は当たり前のようにあったんです。
#灰皿も頻繁に飛んでいました
「名前をつける」というのは誕生の儀式であり、「キミがココにいることを認める」ということなので、ルビッチに「プペル」という名前をつけさせました。
そんなこんなで本題です。
マーケティングとセールスとクオリティー
時代のルールが秒速で変わる現代では、素早く、しなやかに打ち手を変えていくことが求められるわけですが、その時に必要なのが「名前をつける」という作業だと思います。
というのも、「新しい打ち手」には、かならず説明責任が付いてくるからです。
「お前がやっていることはナンだ?」とゴリゴリに疑ってくる相手に説明する(納得してもらう)には、「相手が知っている情報」や、「相手が理解できる情報」を織り混ぜる必要がある。
たとえば、「作ったものを受けとるのが『お客さん』だろ!」と信じ込んでいる相手に対して、「お客さんと一緒に作っていくエンタメです」と説明しても無駄なので、このアクションに『バーベキュー型』という名前をつける。
その時、相手は、「ん? たしかに、BBQの時は、お金を払って、火をつけたり、肉を焼いたりしてるぞ。あ。それを他のエンタメでもやろうってこと?」となり理解が進みます。
『レストラン型サービス』と『バーベキュー型サービス』という名前をつけたことによって(知ったことによって)、プロジェクトの無駄はかなり省くことができるでしょう。
『人検索』や『プロセスエコノミー』という名前をつけたことによって、僕らの時代は半歩進みました。
「今、自分がやっているアクションの名前は一体、何なんだろう?」
ここを明確にすることが、ものすごーく大切です。
(続きはこちらから【連載「革命のファンファーレ~現代の労働と報酬」】)
【西野亮廣】「『クリエイティブ』というのは『マーケティング』に内包されている一要素である」これがわからない人は、ビジネスに失敗する!?──連載「革命のファンファーレ2」Vol.32
https://goetheweb.jp/person/article/20220304-nishino_akihiro_32