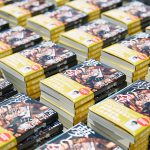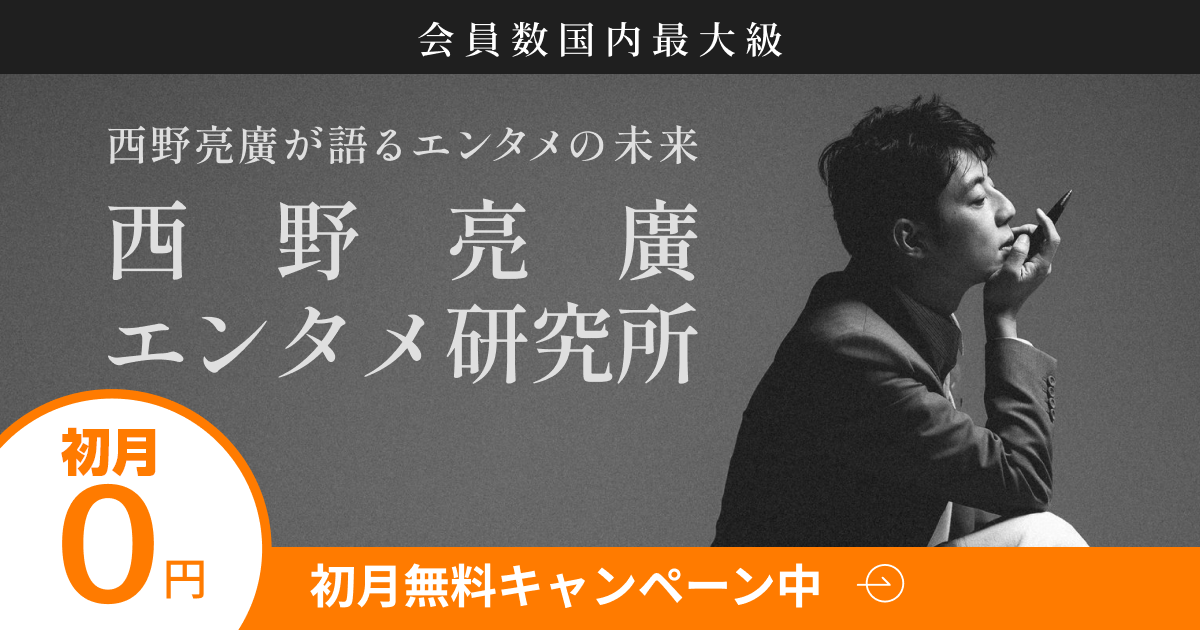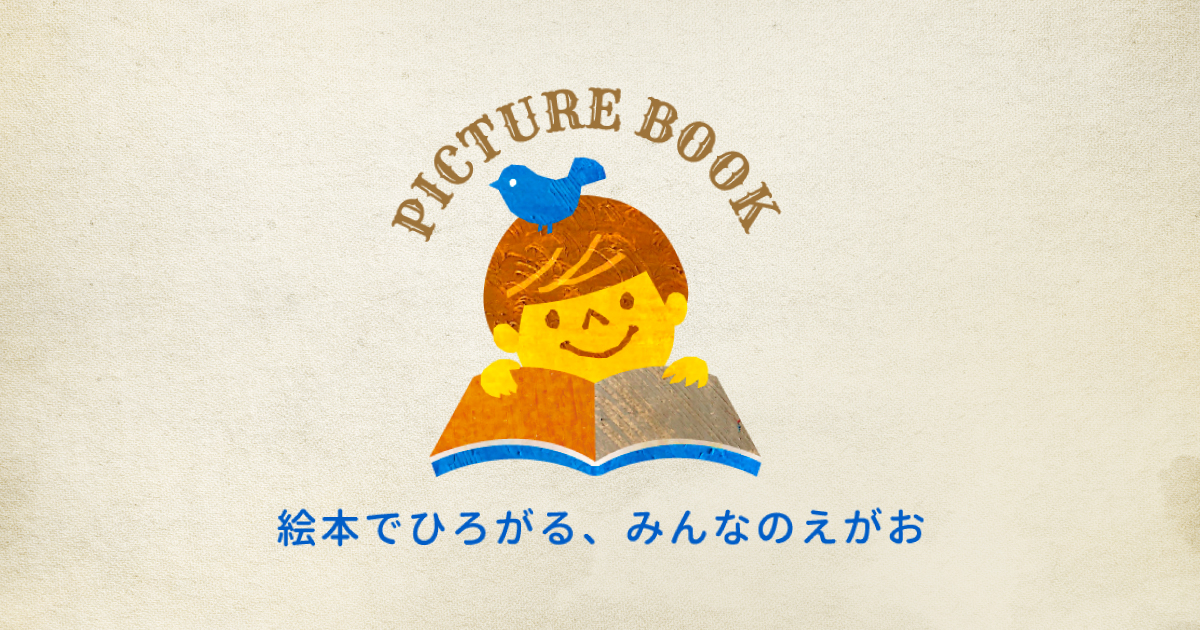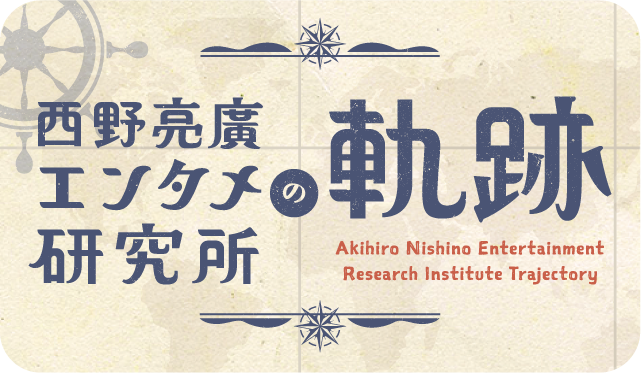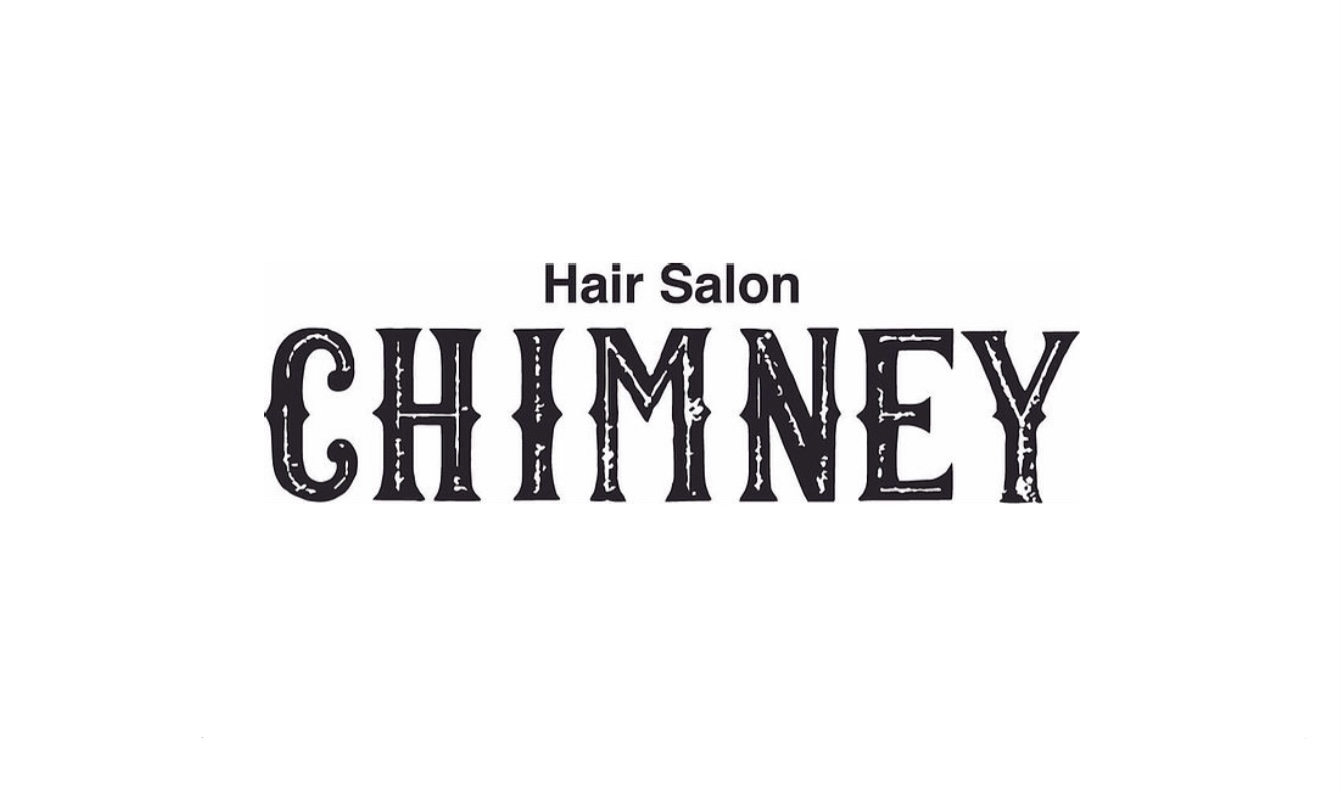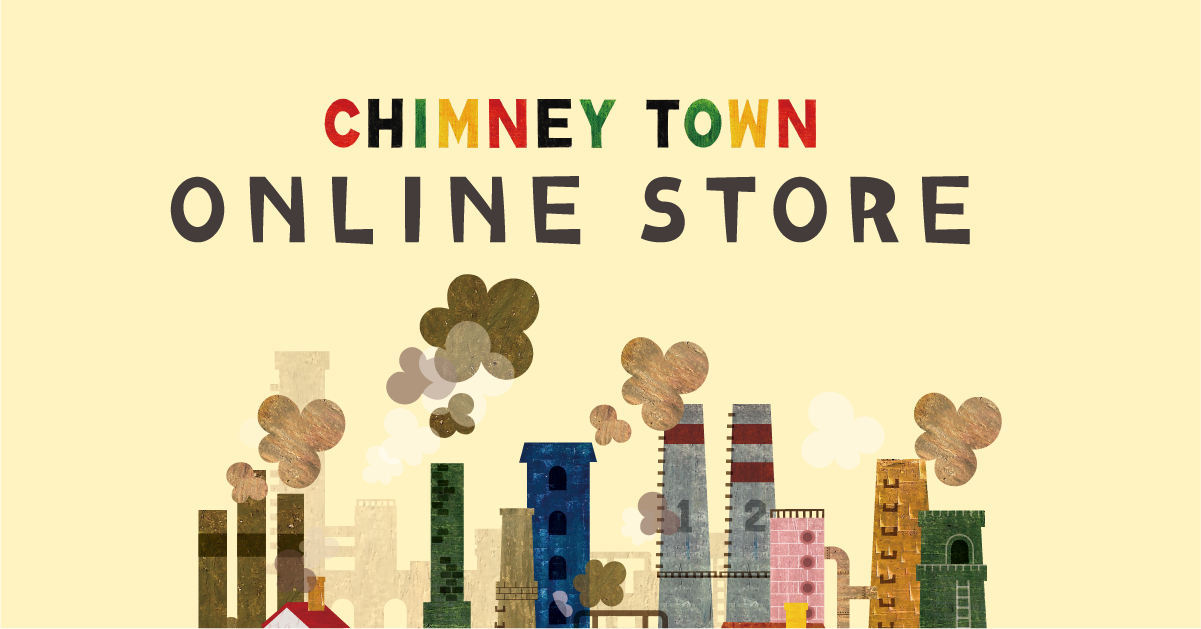『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』のポスターを1万枚配りたい!

(※今日の記事を音声で楽しみたい方はコチラ↓)
https://voicy.jp/channel/941/6909289
日本人が他人をネチネチと監視し続ける理由 | 西野亮廣(キングコング)「西野さんの朝礼」/ Voicy - 音声プラットフォーム
https://voicy.jp/channel/941/6909289
「お金の歴史」は「人類史そのもの」
9月から「キンコン西野の〝親子で通う〟お金の学校」という(全12回の)オンラインスクールがスタートします。
4〜5日前から募集を開始して、現在、受講者数が【420名】を突破しておりまして、大変な盛り上がりでございます。
やっぱり、「我が子にお金の苦労をさせたくない」という親御さんが多いのだと思います。
ちなみに、「お金の学校の動画を、教材として授業で使っていいですか?」という質問が届いておりますが、オフラインで活用する分には構いません。
ただ、「来年以降、その動画を使い回すかどうか?」に関しては、情報の鮮度があるので、あまりオススメはしません。
▼『キンコン西野の〝親子で通う〟お金の学校』のお申込みはコチラから↓
https://chimneytown.net/products/onlineschool-2025-9-2026-8
さて。
そんなこんなで、今日は「お金」に関する少し面白い話をしたいと思います。
Voicyのリスナーさんはもうお察しかもしれませんが、僕は、贅沢の類には一切興味がなくて、べつに「お金持ちになりたい」とも思っていません。
「お金持ち」になりたければ、勝ち逃げできるタイミングなんてこれまで何百回もあったので、とっくになってます。
僕が「お金」に関して興味があるのは「挑戦を続けていく為(エンタメを作り続ける為)の予算」と「お金の歴史」です。
「お金の歴史」と一口で言っても、ヨーロッパのお金の歴史と、中国のお金の歴史と、日本のお金の歴史は、それぞれ違っていて、そこにあるのは「人類史そのもの」なので、掘れば掘るほど面白いんです。
あくまで仮説ですが、「ここで、お金がこういう変化を遂げたから、それをキッカケに人間は、こうなっちゃったんだろうな」というのが随所にあって、今日のタイトルにあります「日本人はなぜネチネチと監視し合うのか?」も、おおよそ「お金の歴史」で説明ができそうです。
まず、今の僕たちは、「円」で税金を納めているじゃないですか。
住民税も所得税も、口座から自動で引き落とされたりして。
ただ、この「円で納める」というスタイルが確立されたのは、ここ150年くらいの話なんで、1300年以上前、奈良時代の日本の税金は「米」や「布」、それから「特産物」で納めていたんです。
この頃の税制度は、「租・庸・調(そ・よう・ちょう)」と言ったりします。
稲を納めるのが「租」、無償労働で貢献するのが「庸」、
そして、特産品──たとえば薬草や織物を納めるのが「調」。
そこから時代が進んで、平安時代や鎌倉時代になると、「年貢(ねんぐ)」という形で、主に“米”を年に一度、納めるようになります。
田んぼの収穫の何割かを納税、ってやつです。
江戸時代になると、いよいよ“米の時代”が本格化。
土地の生産力を「石(こく)」という単位で測って、お百姓さんたちはその石高に応じて米を納めました。
この時代は、米が“通貨”のような役割を果たしていた時代です。
それが大きく変わるのが、明治時代。
1873年に地租改正(ちそかいせい)という制度改革がありまして、税金は“米”じゃなくて“お金”で納めるようになった。
ここでようやく、「円で税を払う」という、僕たちが知っているスタイルが始まったわけです。
「納税」が人間の人格形成にまで及んでいた
さて。
たとえば江戸時代には、「石高(こくだか)」という制度がありました。
これは幕府が各土地の生産力を見積もって数値化したもので、「この土地からは年間これだけの米が収穫できるはずだ」とする、いわば想定収穫量です。
農民たちは、この石高に基づいて年貢を課されており、たとえ凶作や天候不順で実際の収穫量が大幅に下回った年であっても、あくまで“見込み”に従って年貢を納めなければなりませんでした。
そのため、実情に合わない重税が課され、多くの農民が困窮する原因となっていたんです。
そこで農民達は、幕府に見つからないところに「田んぼ」を新たに作ったりなんかして、今で言うところの「脱税」みたいなことをしていたんです。
そうまでしなきゃいけなかった理由は、どれだけ生活に余裕がなかろうが、納税しなかったら激しい罰が待っていたからなんです。
家財を差し押さえられたり、酷い場合は「田畑」を没収されたりしたのですが、なんとこれ「年貢を納めなかった個人」が罰せられるわけではなくて、「年貢を納めなかった個人が所属している村」が罰せられるという連帯責任だったんです。
だから、村人達はお互いに監視し合って、ちょっとでも変なことをする奴がいたら、皆で「おい、コラ!」と迫ったそうです。
幕府に目をつけられる奴が我が村から出たら自分も罰せられるから、「他所は他所、ウチはウチ」というわけにはいかなかったんですね。
「納税」というものが「お金」に価値を持たせているし、我々の人間の人格形成にまで及んでいた‥という話です。
ちなみに、「キンコン西野の〝親子で通う〟お金の学校」では、こんな話はせずに、実際に現場で使える「お金の作り方」「お金の守り方」「お金の使い方」についてお話しするので、ご安心ください。
====================
CHIMNEY TOWNのホームページを、
スマホのホーム画面(待受画面)に追加する方法
====================
★iPhoneの場合
→画面下にある変なマークをクリックしたら、そこに『ホーム画面に追加する』が出るので、そこをポチッと!
★Androidの場合
→画面右上にある「三つの点」マークをクリックしたら、そこに『ホーム画面に追加する』が出るので、そこをポチッと!
【注意】
LINEアプリ(たぶんFacebookアプリも)でホームページを開いてしまうと『ホーム画面に追加する』が出ないので、その場合は、Google Chromeを立ち上げて、『https://chimney.town/』を入力して、そこから、★の手順でチャレンジしてみてねー!
いつも応援ありがとうございます!
「西野亮廣エンタメ研究所」ではオンラインサロンの会費を活動資金として、さまざまなプロジェクトに挑戦しています!
▼メンバーになって西野の挑戦をもっと応援したいという方はコチラ
「西野亮廣エンタメ研究所」
https://salon.jp/nishino
日本人が他人をネチネチと監視し続ける理由 | 西野亮廣(キングコング)「西野さんの朝礼」/ Voicy - 音声プラットフォーム
https://voicy.jp/channel/941/6909289
※サロンメンバーさん同士交流される場合は今まで通りFacebookアカウントが必要です
\公式LINEができました/
▼西野亮廣 公式LINEはコチラ↓
https://lstep.app/bew62ko